「全員一律」から「一人一人の最適解」へ
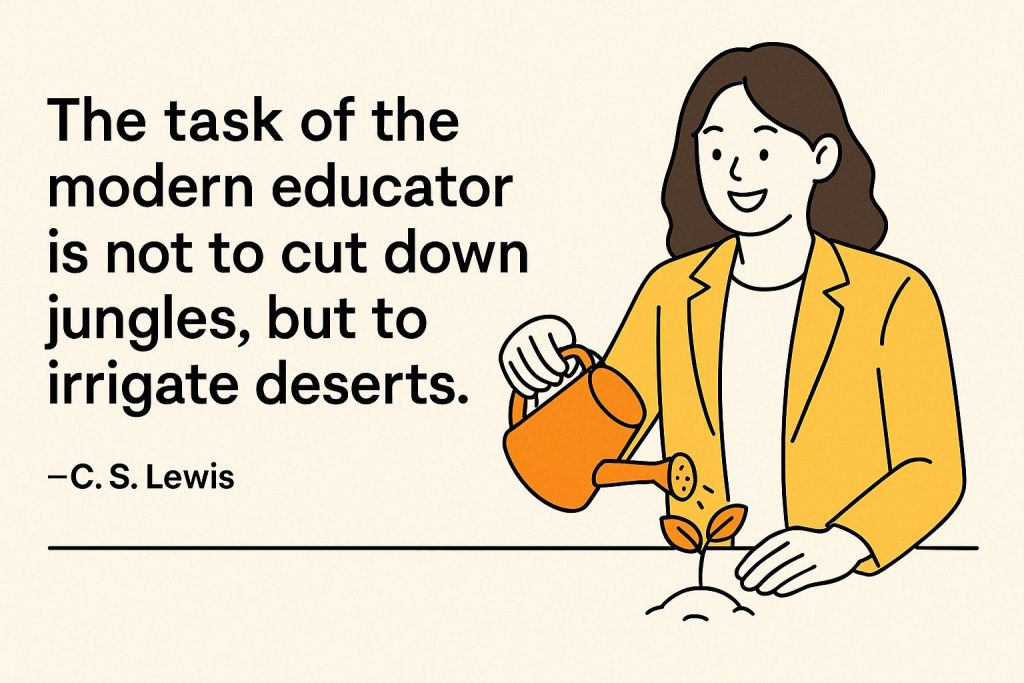
かつて私は、未来技塾という集団指導型の塾で、多くの生徒たちと向き合ってきました。
教室の前に立ち、同じ時間に、同じ内容を、全員に向けて一斉に教える――。
それが当時のスタイルでした。
しかし、私の中で一つの疑問が生まれます。
「本当に、全員に同じことを同じように教えるだけで、
生徒一人一人が『自分の目標とする学力』にたどり着けるのだろうか?」
その問いへの私なりの答えは、「NO」でした。
生徒はみんな「違う」からこそ、同じでは届かない
生徒たちは、それぞれに違います。
性格も、記憶力も、思考のスピードも、
得意科目も苦手科目も――。
教育心理学の観点でも、人間の「認知スタイル」や「学習スタイル」は個人差が大きいことが示されています。
同じ教材・同じ教え方であっても、それを受け取る子どもたちの理解の深さやスピードはまったく異なります。
さらに、脳科学の分野でも、繰り返し・自己主導・タイミングのよい復習こそが、
長期記憶への定着に有効であるとされており(Ebbinghausの忘却曲線など)、その「タイミング」すら個人差があるのです。
つまり、「全員一律のインプット」では、本来の力を発揮できない生徒が、必ず出てきてしまうのです。
学びの持続には、「見える化」と「カスタマイズ」が必要
マナラボでは今、「一人一人が自分の目標とする学力にたどり着けるようにする」ことを、最も大切にしています。
そのためにまず取り組んでいるのが、学習内容や学習時間の『見える化』です。
そして、それをもとにしたツールの活用や、持続可能な学習設計の提案。
これは、心理学で言う「自己決定理論(Self-Determination Theory)」とも深く関わります。
人は自分で「選べる」「調整できる」と感じたときに、より深く、より継続的に学びに取り組めるのです。
AI・ICTの活用で、教える以上の「支える」を
正直に言って、これからの学びにおいてAIやICTの活用は欠かせません。
「教えること」は、もはやAIやICTが担う時代です。
だからこそ、先生が担うべき役割は、「教える人」ではなく「支える人」へ。
生徒の進捗を見守り、必要なタイミングでアドバイスし、軌道修正してあげる。
それが、これからの先生の役割だと思っています。
同じ教材、同じ進度、同じ教え方ではなく、「その子にとっての最適な方法」を一緒に探していく。
これが、マナラボが目指す、未来の教育のかたちです。
最後に
私たちは、「わかる」だけではなく、
「続けられる」学びを大切にしたい。
そして、生徒一人ひとりの目標とする学力に、
しっかりたどり着けるように、寄り添っていきたい
これまでの「一斉授業型」のスタイルから大きく舵を切った今、
私たちの教室は、新しい学びの地図を描き始めています。
守田 智司
最新記事 by 守田 智司 (全て見る)
- 【令和8年度】愛知県公立高校 推薦選抜・特色選抜 志願者数と倍率の動向まとめ - 2026年2月3日
- 日曜日の自習室から見える高校生たちの本気 - 2026年1月18日
- 今日は工房てつへ|木の小人が迎えてくれました - 2026年1月15日
- 学年末テスト1か月前 - 2026年1月13日
- 中1・中2のみなさんへ 学年末テストは「1年のまとめ」――だから、今からが勝負です - 2026年1月11日

