正解は教えない。考える力を育てる。
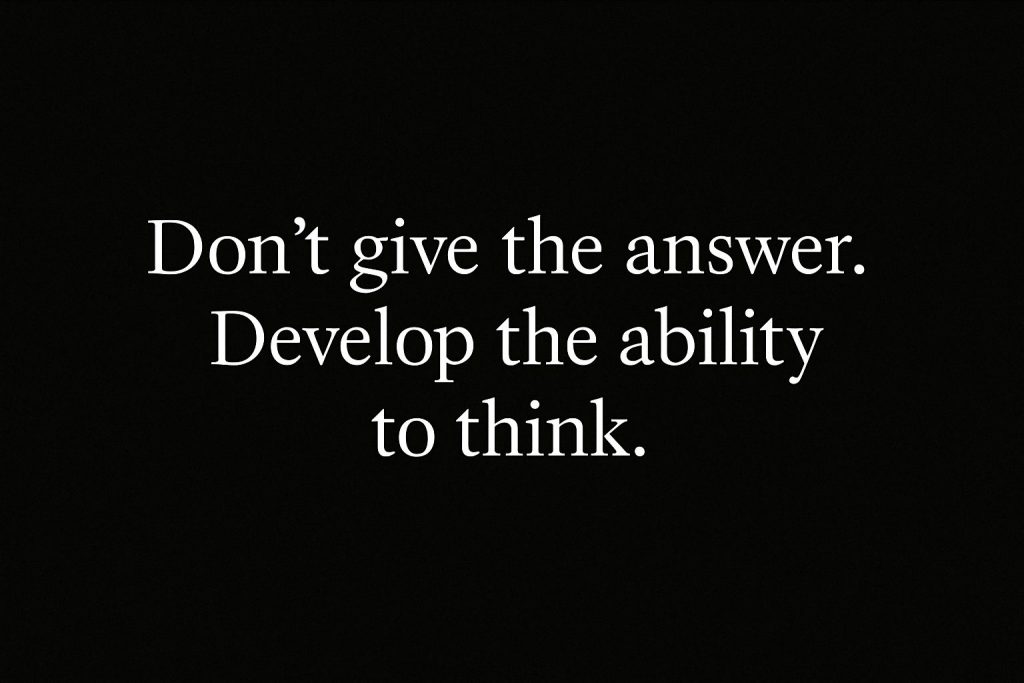
25歳から40歳まで、私はいくつかの大手の学習塾でサラリーマンとして働いてきました。
当時は、「いい会社だな」と思っていましたし、そこにいることに疑問を持ったことはありませんでした。
でも今、60歳を迎え、ふとあの頃を思い返してみると――
ある意味で「教団」のようなものだったのではないかと感じています。
日本の企業文化は、「共同体」よりも「教団」に近い。
心理学的にいえば、“同調圧力”と“帰属欲求”の中で、「自我」よりも「役割」が優先される社会です。
一度その組織に入ってしまえば、あとは命を削って長時間働くことが“当然”とされる。
そういう時代を、私は生きてきたのだと思います。
目の前の仕事に全力を尽くす日々。
けれど今思えば、それは“自分の思考”ではなく、“会社の思考”に染まりきっていた日々でもありました。
知らず知らずのうちに、自分の意志よりも、組織の意志に従っていたのです。
もちろん、そういう働き方を否定するつもりはありません。
でも――
先日、60歳の同窓会に参加したとき、あることに気づきました。
そこには、すでに定年を迎えた仲間たちが何人もいました。
中には、まるで魂が抜けてしまったような、そんな表情をした友人もいました。
長年必死に働き、役割を果たしてきたはずなのに、
その先に“空白”しか残っていないような光景を目の当たりにしたのです。
「一体、私は何のために働いてきたのか――?」
その問いが、心にずっしりとのしかかってきました。
今、もう一度、自分自身の“これから”を見つめ直しています。
“役割”ではなく、“自分自身”としてどう生きるか。
働き方の変化
会社を辞めて、自分で塾をやりはじめた今、働き方も、生き方もまるで違います。
誰かに決められた仕事ではなく、自分で考えて、自分で決めて、自分で動く。
「誰かの評価」ではなく、「自分が何のためにそれをやるのか」を、常に問われ続けます。
自営業というのは、自由でもあるけれど、厳しい。
でも、そこには“自分で生きる”という手ごたえがある。
学校では教えてくれなかった“力”
振り返ると、学校や会社で教えてもらったことの多くは、
正直、今の仕事ではあまり役に立っていないと感じるんです。
それよりも必要なのは、自分の頭で考える力、自分の言葉で伝える力、
そして社会に向けて発信していく力。
これらはまさに、「プレゼンテーション力」や「主体性」「共創力」といった、
今の教育界でも重視されている“非認知能力”といえるでしょう。
これからの国際社会では、知識だけでは生きていけない。
だからこそ、子どもたちにも、AIや情報技術を“使う側”になってもらわないといけないと思います。
AIができることじゃなく、“人間にしかできないこと”を育てる教育が必要なんです。
子どもたちを取り巻く現実と、教育のこれから
現場では、はっきりと「できる子」と「できない子」の差が広がってきています。
まるでブラックボックスのように、家庭環境や情報量の違いが、
学力差をそのまま“生きる力の差”に変えてしまっているように感じます。
教育心理学でよく使われる「自己効力感(self-efficacy)」という言葉があります。
これは、「自分はやれる」という感覚のこと。
学力とは、単なる点数ではなく、
この“自己効力感”を育てるかどうかで決まる部分がとても大きいと思います。
教育とは、「想像力」と「希望」を育む場所
私は、教育というのは単に知識を教える場所ではなく、
“その子がその子として生きていくための土台をつくる場”だと思っています。
AI、IT、グローバル化、多様性…これからの社会は、今までの常識が通用しない時代です。
でもだからこそ、人間が持つ「想像力」「感受性」「創造力」が、より大きな価値を持ってくる。
教育の役割は、変化の時代の中で、
子どもたちに“変化していく勇気”と“希望を持ち続ける力”を与えることじゃないかと、心から思うんです。
60歳は、ただの“終わり”ではなく、“再出発の入り口”です。
若いころのような体力はないかもしれないけれど、
その分、思考や経験を“次の世代のため”に使える年齢になったとも言えます。
これからの人生は、「自分のため」ではなく、「次の世代のため」に。
僕の小さな塾から、子どもたちの未来を少しでも支えていけたら。
❝ 正解のない問いを、自分で考え、自分の言葉で語る。そこに教育の価値がある。❞
– 齋藤孝(教育学者)
守田 智司
最新記事 by 守田 智司 (全て見る)
- 令和8年度愛知県公立高校推薦選抜合格者数・倍率【三河学区】 - 2026年2月10日
- 【令和8年度】愛知県公立高校 推薦選抜・特色選抜 志願者数と倍率の動向まとめ - 2026年2月3日
- 日曜日の自習室から見える高校生たちの本気 - 2026年1月18日
- 今日は工房てつへ|木の小人が迎えてくれました - 2026年1月15日
- 学年末テスト1か月前 - 2026年1月13日

