男子反抗期は脳の設計図通り
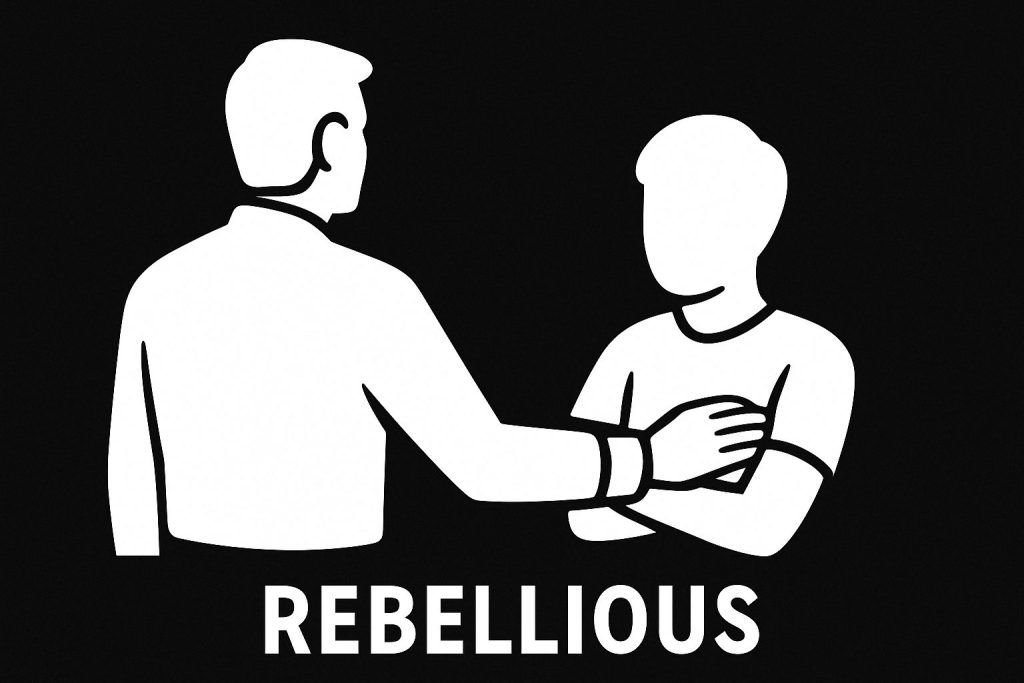
「最近、うちの息子がやたらイライラしてる……」
「何気なく声をかけただけでキレられた……」
そんな風に、思春期の男の子に手を焼いているご家庭も多いのではないでしょうか。
私自身、反抗期を迎えた子どもを前に「どうしてこんなに反抗的になっちゃったの?」と悩む場面がありました。
でも、脳科学者・中野信子さんの著書『キレる!』を読んで、その理由がとてもよくわかったんです。
テストステロンの分泌と“男の子の脱皮”
思春期の男の子の体には、大きな変化が起きています。
その中心となるのが、男性ホルモン「テストステロン」。
これは、精巣(こうがん)で作られ、脳にも作用します。
その影響で、
声変わり
体毛やヒゲの成長
筋肉の発達
など、身体は一気に“男の体”へと変わっていきます。
テストステロンの分泌は15歳前後でピークを迎えるとされ、
これはまさに“子ども”から“男性”への脱皮の時期でもあるのです。
心の変化も同時に起きている
テストステロンは心にも影響を与えます。
一人でいたいと感じるようになる
親子の距離をとりたがる
支配欲や攻撃性が高まる
つまり、家族と一緒に過ごすよりも、自分の部屋で一人でいる方が心が落ち着く時期。
これは決して親を嫌っているわけではなく、心の自立の第一歩でもあるのです。
この変化は心理学でいう「アイデンティティの確立」にあたります。
エリクソンの発達理論では、思春期は”自我同一性 vs 同一性の拡散”という課題を乗り越える時期とされており、
まさにこのタイミングで「自分は何者か」を模索する心の葛藤が強くなっていきます。
「脳の未発達」がイライラを加速させる
中野信子さんの本でも語られていますが、
思春期の脳、特に“前頭前野”と呼ばれる感情をコントロールする部分は、まだ成長途中です。
そのため、
怒りや衝動を抑える力が弱い
ブレーキが効きにくい
という状態にあります。
つまり、「キレやすい」「すぐ怒る」のは、脳が未熟だからこそ。
本人も、なぜこんなにイライラするのか分からないことが多いのです。
教育学的な視点から見ても、この時期は「認知発達の過渡期」であり、
抽象的な思考や論理性が未完成なまま感情だけが先走る傾向があります。
そのため、大人のように
「状況を整理してから発言する」
「一呼吸おいて対応する」
といった行動が難しく、衝動的な言動につながりやすいのです。
親のせいじゃない。だから、まずは安心して。
「私の育て方が悪かったのかな……」
「家庭環境に問題があったのかも……」
そんなふうに、自分を責めてしまう親御さんも多いと思います。
でも、これは誰にでも訪れる成長のプロセス。
思春期の男の子は、誰に対してもイライラします。
だからこそ、親は「自分のせいかも」と思い込まないことが大切です。
叱るよりも、“背中で見せる”
この時期の子どもに、言葉で説教しても、ほとんど伝わりません。
言葉で理解することが、まだ難しいのです。
ではどうするか?
答えは「背中で見せること」。
細かく口を出すのではなく、
でも目は離さずに、
自立をそっと支える
これが、親としてできる最も健全な関わり方ではないでしょうか。
特に父親は、グチを言わずに黙って働く姿、家族を支える姿を見せることが、子どもにとって一番の教えになることがあります。
また、教育的視点からは「モデル学習(模倣学習)」という考え方があります。
子どもは言葉以上に、親の行動や姿勢を観察し、そこから社会的行動を学んでいきます。
親の“生き方”こそが、子どもにとっての教科書なのです。
まとめ:キレるのは、成長の証
15歳の男の子が反抗的になるのは、「大人になろうとしている証」です。
心も体も大きく変わる中で、自分自身でもどうしていいか分からない時期。
そんな時こそ、親が落ち着いて、
「キレるのも成長の一部なんだ」
「いずれ、あの頃もあったねって笑える時が来る」
と信じて、静かに見守ってあげてください。
子育てに正解はありません。
でも、「安心してそばにいてくれる存在」があるだけで、子どもは強くなれます。
脳科学、心理学、教育学の知見から、少しでも思春期の男の子との関わりが楽になれば。
そんな想いで、この文章を綴りました。
守田 智司
最新記事 by 守田 智司 (全て見る)
- 【実質倍率0.98倍】|令和8年度 愛知県公立高校一般選抜 志願状況 と三河学区の主な高校の倍率 - 2026年2月16日
- 令和8年度愛知県公立高校推薦選抜合格者数・倍率【三河学区】 - 2026年2月10日
- 【令和8年度】愛知県公立高校 推薦選抜・特色選抜 志願者数と倍率の動向まとめ - 2026年2月3日
- 日曜日の自習室から見える高校生たちの本気 - 2026年1月18日
- 今日は工房てつへ|木の小人が迎えてくれました - 2026年1月15日

