「授業が速くてついていけない…」と感じる前に――高校1年生にとって“予習”がなぜ大切か?
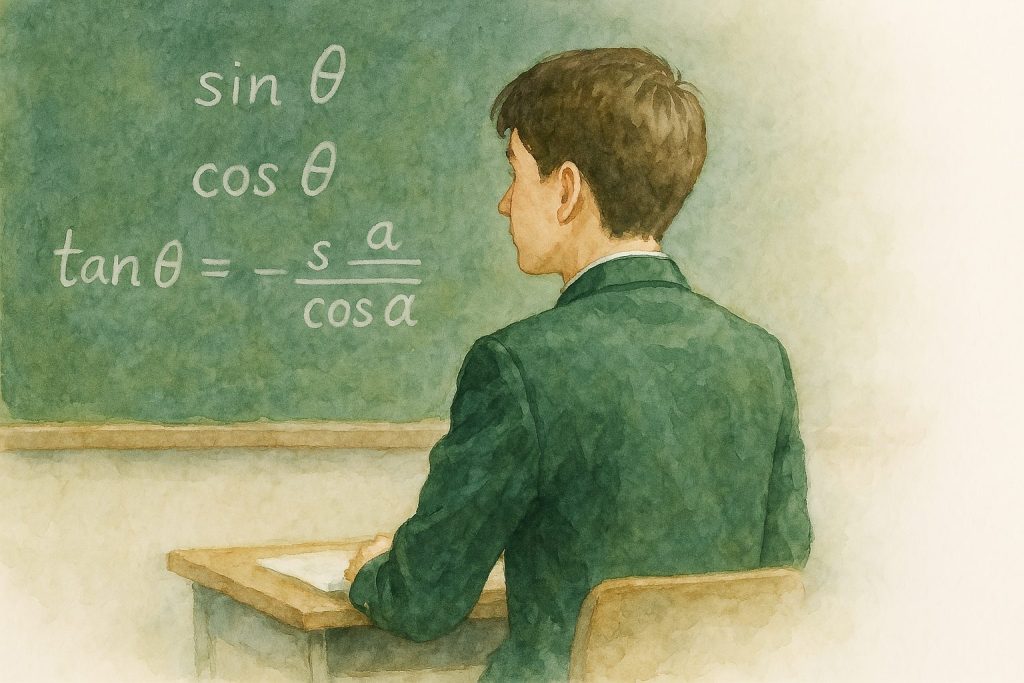
「高校の授業、めちゃくちゃ速くてついていけない…」
これは、ある高校1年生の生徒が、入学してまだ2週間ほどしか経っていない4月中旬に漏らした一言です。
入学当初は期待と不安でいっぱいだった彼女。ところが、実際に授業が始まってみると、そのスピードの速さに驚いたといいます。特に数学I(数Ⅰ)の授業では、先生がどんどん黒板に問題を解きながら進んでいく。ノートを取るのに精一杯で、内容の理解が追いつかない子が続出しているそうです。
そんな中、彼女はこう話してくれました。
「私は3月からマナラボで数Ⅰと数A、英語の予習をしていたので、授業はよくわかります。予習をしていなかった周りの子たちは、全然ついていけないって言っていました。先生が予習が大事って言っていた意味が、初めてわかりました」
この一言には、高校学習における「予習の価値」が詰まっていると思います。
なぜ高校では予習が必要なのか?
中学とは違い、高校では授業の進度が一気に上がります。文部科学省の指導要領もある程度ベースになりますが、それでも1時間の授業での情報量は中学と比べて数倍。特に進学校では1週間で数十ページが進むことも珍しくありません。
そのため、予習をしていない状態では、
新しい知識を授業中に「初見」で受け止めようとする
難しい用語や数式を一度で理解できずに置いていかれる
ノートを取るのに必死で、思考する余裕がない
といった事態が起きやすくなります。
一方で、予習をしている生徒は、
あらかじめテキストに目を通して、重要語句や例題をチェック
授業中は「確認」のつもりで聞けるので、集中力が分散しない
疑問点も明確になっているため、質問ができる
というように、「理解を深めるための時間」として授業を活用できるのです。
予習は“できる子”だけがやるものではない
「予習って、勉強ができる子がやるもの」
と思っている生徒も多いかもしれません。
しかし、実際はその逆です。
“わからなくなる前に、自分を守るために予習する”のです。
予習は、勉強の「武装」です。教科書を読んで、わからない言葉に印をつけて、例題を少しだけでも解いてみる――それだけで、次の日の授業が“まるで別物”に感じられます。
「予習」の習慣をつける最初の一歩
まずは「教科書を読む」だけでもOKです。
もっと言えば「タイトルと太字だけ読む」「1ページだけやってみる」でもいい。
大事なのは、“授業が初見にならない状態”をつくること。
自分の学習を“受け身”から“能動的”に切り替えるだけで、理解度が大きく変わります。
マナラボでは、入学前から“先手の学び”を大切にしています
今回の高1生のように、マナラボでは春休みから予習を進めていたことで、「高校の学び」にスムーズに入れている子が多くいます。
中学とは違う「高校」というステージで、自分のペースを崩さず学ぶためにも、予習の大切さを伝え続けていきたいと思っています。
最後に:高校の授業に“ついていける”自分をつくるために
「まだ始まったばかりだから…」
「とりあえず授業を受けてから…」
そう思っているうちに、授業はどんどん進んでいきます。
“わからない”を“わかる”に変えるには、授業の前の5分、10分の行動が鍵になります。
予習は、未来の自分へのプレゼントです。
高校生活、つまずかずにスタートを切るためにも、ぜひ今日から小さな一歩を踏み出してみてください。
守田 智司
最新記事 by 守田 智司 (全て見る)
- 令和8年度愛知県公立高校推薦選抜合格者数・倍率【三河学区】 - 2026年2月10日
- 【令和8年度】愛知県公立高校 推薦選抜・特色選抜 志願者数と倍率の動向まとめ - 2026年2月3日
- 日曜日の自習室から見える高校生たちの本気 - 2026年1月18日
- 今日は工房てつへ|木の小人が迎えてくれました - 2026年1月15日
- 学年末テスト1か月前 - 2026年1月13日

