司馬 遼太郎「峠」河井継之助ふたたび・・・
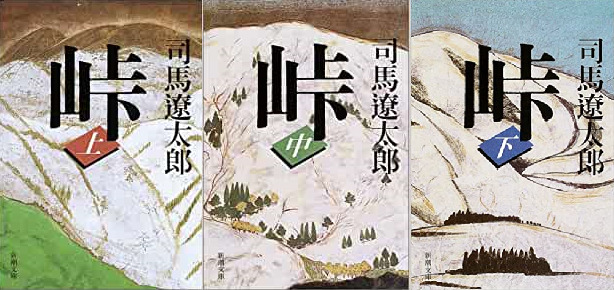
最近、司馬 遼太郎の峠を再び読み始めている。
最初に、読んだのは今から8年前。
長岡藩士として中立を守り、
理想とした長岡公国を作りたかった河井継之助の生きざまは、
再びページをめくりながら、ぐっと引き寄せられ、魅了する彼の生き様がありました。
攻める相手を失った薩長が会津を朝敵とし攻撃するも、
その間に入り停戦させようとした河井継之助。
維新史上最も壮烈な北越戦争に散った河井継之助。
どこにも属さない、
独立国という世界を作ろうとする想いと裏腹に歴史は、官軍と戦う選択を突きつける。
再び読み返していて、
河井継之助の生き方に絶えず「志」を感じさせてくれる。
日常を怠惰と数多くの妥協にまみれて生きている私に、
継之助の生き方は、
「何か」を指し示してくれているような気がしました。
「峠」の一節に
人はどう行動すれば美しいか、
ということを考えるのが江戸の武士道倫理であろう。
人はどう思考し行動すれば公益のためになるかということを考えるのが江戸期の儒教である。
この二つが、幕末人をつくりだしている。
2005年、塾を開校するなら、
自分が生まれた「蒲郡」だと考えていたし、
地域に根差し、その中で自身の役割を担い生きる場所だと決めていました。
改めて、「峠」を読み返しながら
「自分に何ができるのか?」
塾人として、市民として、
その思考と行動が公益のためになるのか?
この小さな塾に大切なお子さんを通塾させてくれている保護者の皆さんに何ができるか?
「私」と「公」のバランスを考え、
自分の想い描く、「理想の塾」に向かい、
己の「志」を忘れることなく
改めて孤軍奮闘していきたい思いました。
泣ける、泣けた場面
再び読んでいて、涙が止まらない場面がありました。
長岡城が陥落。
馬上から1人、
逃げ惑う民衆に対して敗戦を詫びながら
「気の毒であった」
「しかし御家はみなを捨てぬぞ。食い物がなくなれば、本陣へ来よ。」
「たとえ兵糧に事欠いても、一粒の米を二つに砕き、三つに砕いても食わせるぞ。」
と叫んで回った場面です。
司馬 遼太郎「峠」を読んでいて心に残る言葉たち
人間はその現実から一歩離れてこそ物が考えられる。
距離が必要である、 刺戟 も必要である。
愚人にも賢人にも会わねばならぬ。
じっと端座していて物が考えられるなどあれはうそだ─
この時代、人に会うこと以外、自分を啓発してゆく方法がなかった。
天下の士は、そのために諸国を周遊している。
かれの思想では、学問はその知識や解釈を披露したりするものではなく、行動すべきものである。
その人間の行動をもってその人間の学問を見る以外に見てもらう方法がない。
三河の当時、土豪牧野氏はその勢力は自家の力でつくりあげたとはいえ、戦国のならいでより強大なるものに所属していた。被官というありかたであった。東隣する大勢力である 駿河・遠江(あわせて静岡県) の今川氏に属し、その指揮をあおいでいた。継之助はつねづね牧野氏の家系を考えるとき、(この御家の運命の数奇さよ)とおもう。
守田 智司
最新記事 by 守田 智司 (全て見る)
- 日曜日の自習室から見える高校生たちの本気 - 2026年1月18日
- 今日は工房てつへ|木の小人が迎えてくれました - 2026年1月15日
- 学年末テスト1か月前 - 2026年1月13日
- 中1・中2のみなさんへ 学年末テストは「1年のまとめ」――だから、今からが勝負です - 2026年1月11日
- まず、やってみる一年へ。 2026 - 2026年1月2日

